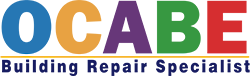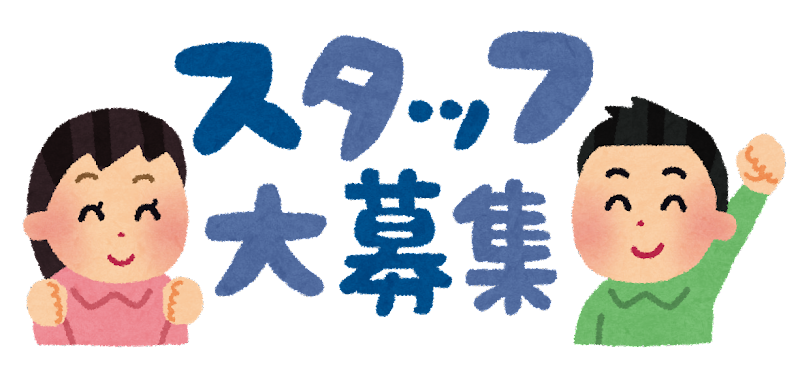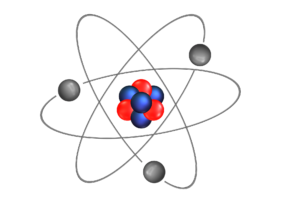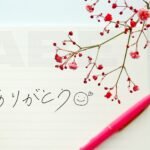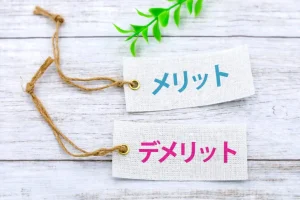コンクリート造の建物は雨漏りがつきものなのか?
コンクリート造の建物は高級感もアリ、デザイン的にも素敵な建物が多いですが、なぜか築数年で雨漏りが起こるというジンクスがあります。
大きな雨漏りもありますし、染み出すような原因不明の雨漏りもあり、悩んでいる方も少なくありません。
コンクリート造建物が雨漏りする理由
コンクリート造建物の多くは陸屋根で防水が施してあります。屋根とは異なり、防水層は清掃も含めた定期的なメンテナンスが欠かせません。しかし、多くの建物は清掃もメンテナンスもおろそかで、雨漏りが起きてはじめて慌てるということが多いです。必要なメンテナンスがなされていない場合は、当然ですが、雨漏りの原因になることがあります。
でも、原因はそれだけではありません。防水層が上手く雨水をコントロールできていないと、それが原因で雨漏りすることもあります。これに関しては施工の問題もあるのですが、ほとんどの方が雨漏りをすると建築した会社に頼りますので、原因が不明となってしまうというわけです。お気づきでしょうが、建築した会社がミスをしているから雨漏りが起きているわけで、それに気づくのはその会社よりも技術が高い会社でないと分からないです。
屋根部分以外の雨漏り原因
原因不明の雨漏りが多いのもRC造建物の特徴です。
それらの多くは、普通の建築会社では思いもよらぬ場所であることが多いです。例えば、建物に引き込まれている電線であったり、窓周りの施工の悪さだったり・・・・弊社は多くのケースを経験してきていますので、そこから判断し探し出すことが出来ますが、一般的な建築会社では難しいことが多いです。
コンクリート造の雨漏り修繕(完成版・専門編)
1. 雨漏り調査の専門的手法
赤外線サーモグラフィー調査
外壁や屋上スラブに赤外線カメラを用い、日射や放熱による温度差を可視化。含水部は熱伝導率が異なるため「低温領域」として判別できます。ただし、環境や天候によっては診断ができないことがあるだけでなく、使用者の知識や経験でも結果が異なるため、あくまでも補助的な調査方法です。逆に考えると、この方法を前面に出す会社は信用ならないとも言えます。
散水試験
防水層の立上り部や目地周辺に散水し、室内側から水の浸入状況を観察する方法です。しかし、降雨とは異なるため、ほとんどのケースで正確な判断とはならないため、試験方法の一つにあると認識しておく程度でよいです。この方法を取りたがる会社の技術力も疑った方がよいでしょう。
-
JASS 8(建築工事標準仕様書・同解説 防水工事)に準拠。
-
試験時間や散水量を記録し、再現性を確認。
打診・目視検査
コンクリート表面の浮き・はがれをチェックし、クラックの有無を確認します。0.2mm以上のクラックは雨水浸入経路となりやすいですが、建物の構造や雨がかかる状況にもよりますので「クラック=雨漏りの原因」というわけではありません。
-
クラックスケールによる幅計測
-
中性化試験(フェノールフタレイン法)で鉄筋腐食の危険度も評価
2. 代表的な雨漏り原因と施工不良事例
- 防水層の劣化:表面の破断や接合部からの剥がれなど
-
防水層の端末処理不良:立上りと平場などの取り合い部で剥離
-
シーリング不足:サッシ周り、打継ぎ目地部の施工不良
-
排水計画の不備:ドレン径不足や水勾配が確保されていない陸屋根
- 排水不良:排水部分の詰まり
3. 修繕工法の詳細
(1) ウレタン塗膜防水(密着工法・通気緩衝工法)
-
密着工法:既存防水層が健全な場合に施工できますが、通常の改修では行えません。下地プライマー+ウレタン樹脂塗布。
-
通気緩衝工法:含水下地の場合に有効なので、通常はこちらの工法を採用します。絶縁シートを設置し、水蒸気を逃がす通気口を設置。
(2) シート防水(塩ビシート・ゴムシート)
-
熱融着や接着剤で固定。耐久性は10〜20年。シートの種類によります。
-
屋上スラブに適し、改修工事で広く用いられています。
(3) シーリング打替え
-
サッシまわりや外壁目地に打設。
-
特にRC造では「二次防水」として重要です。2面接着を基本としますが、3面接着で行う必要がある場所もあります。
(4) ひび割れ補修(Uカットシール充填・エポキシ樹脂注入)
-
Uカット工法:クラックをカッターでU字状に掘削 → プライマー塗布 → シーリング材(通常はエポキシ系シール材を使用)充填 (補修痕が残りやすいので、現在は積極的には採用しないものですが、古い技術(知識)の会社は、こちらをメインに行っています。
-
エポキシ樹脂注入工法:0.2mm以上のクラックに低粘度樹脂を圧入
- ノンカットフィルム工法:清掃・プライマー塗布→特殊フィルム+加熱→特殊カバー塗材(粉塵・騒音・アスベストも発生せず、肉やせもしないので、補修痕は殆どわかりません。)
4. 長期維持のためのメンテナンス計画
-
定期点検:屋上・外壁を5年ごとに診断
-
防水層再塗装:10年目でのトップコート再塗布等
-
改修周期:防水層の全面改修は15〜20年が目安
なお、建築物の防水改修は、使用する工法や材料、建物の用途・環境条件によって耐用年数や点検周期が異なります。
一般的な 防水改修のサイクル表(目安) を下に示します。
防水改修サイクル(目安)
| 防水工法 | 点検周期 | 補修周期(部分補修) | 改修周期(全面改修) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルト防水(露出) | 年1回 | 10〜12年 | 20〜25年 | 耐久性が高いが重量あり |
| アスファルト防水(押えコンクリート) | 年1回 | 12〜15年 | 25〜30年 | 紫外線の影響を受けにくい |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | 年1回 | 7〜10年 | 15〜20年 | 紫外線や熱に注意 |
| ウレタン塗膜防水(密着工法) | 年1回 | 5〜7年 | 12〜15年 | 下地の動きに弱い |
| ウレタン塗膜防水(通気緩衝工法) | 年1回 | 7〜8年 | 15〜20年 | 下地の湿気を逃がしやすい |
| FRP防水(露出) | 年1回 | 7〜8年 | 12〜15年 | 紫外線・熱で劣化が進みやすい |
ポイント
-
年1回の点検(ひび割れ、膨れ、シーリング劣化、ドレンまわりの詰まり確認など)が必須。
-
補修周期では トップコートの塗替え や 部分補修 を行い、全面改修までの延命を図る。
-
環境条件(沿岸部・寒冷地・日射条件)や使用状況によって寿命は前後する。
まとめ
コンクリート造の雨漏りは、下地劣化・施工不良・排水不良が複雑に絡み合うため、原因特定には専門的な診断が必須です。修繕においても、防水工法の選定を誤れば再発リスクが高まります。
岡部塗装店では、赤外線調査・散水試験を組み合わせた診断と、ウレタン・シート防水・注入工法など現場条件に最適な修繕方法をご提案し、再発しない雨漏り修繕を実現しています。