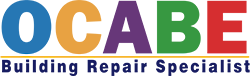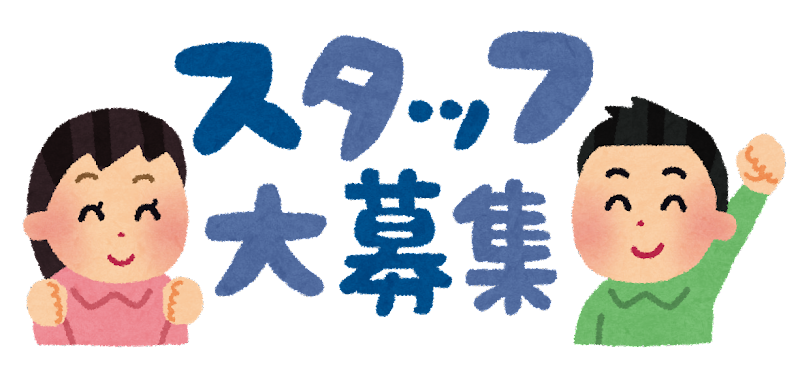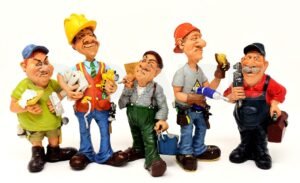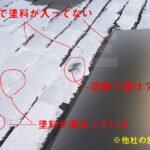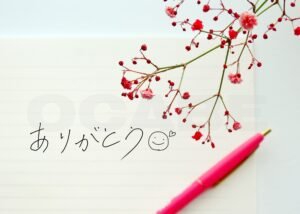下請職人を偽装 「塗装は自社職人」が真実とは限らない
「自社職人で工事をしています。」といった広告をみることがありますが、それは絶対の安心を保証する言葉なのでしょうか?また、自社職人という言葉を信じてよいものなのでしょうか?(ここで言う自社職人とは、通常自社施工すべき塗装等の職人で、足場や熟練が必要な特定種の防水工事などの職人は除きます。)
今回は、業界の闇ともいえる、職人の所属問題について書きたいと思います。
自社職人と下請職人の定義
自社職人とするには、以下の要件にあてはまる必要があります。
- 雇用契約がある
- 会社で社会保険に加入している
- 有給がある
- 雇用保険に入っている
- 会社で日常的に指導をしている
- 請負契約ではない
会社組織になっていない5人以下の個人事業主の元に勤める場合は社会保険に加入する義務はないですが、基本的にこの❶~❻の全てに当てはまらなければ、社員とは言えません。当然自社職人とも言えないので自社職人のように見えても下請です。
特に❺や❻に当てはまらず、1棟いくらで工事を行っているような場合は、自社職人と称していても間違いなく下請職人です。
社会保険がない?!下請職人たちを取り巻く厳しい環境
建設業界の社会保険加入率は未だに3割ほどで、そのほとんどが建設会社の社員やリフォーム会社などのその他会社では職人以外の営業や事務の社員であるため、実際に現場で働く職人たちで加入していないといった厳しい現実があります。
「社員なのに加入してもらえないの?」と疑問に思う方も多いかと思いますが、建設会社の社員の場合は総じて社会保険には加入しています。問題なのは下請会社の所属として働く職人たちです。
社員でない職人たち
社会的な問題ともなっていますが、建設業界の下請け業者は未だに多くが社会保険に未加入です。法人としての登記がなく5人未満の会社ならば社会保険に加入しなくても良いので、それに該当するケースもありますが、例え資本金が1円であっても法人登記がしてある場合は例外なく社会保険に加入しないといけません。しかし、残念ながらこのルールを守らない法人が少なくありません。
理由はいろいろあります。社会保険に加入するには、原則として加入者と企業で1/2ずつ保険料を負担しないといけません。労働者からは自己負担分を徴収しないといけないのですが、これに激しく抵抗する職人は少なくありません。それに会社側も負担をすることをベースでの経理が出来ていないといった問題の他、給与が毎月決まっているわけではなく保険料の計算が難しいと考える経営者が多いといった事情もあります。
自社職人と称されながら未加入の場合は、実際は社員ではなく外注扱いです。リフォーム会社や塗り替え会社の場合、この状態で不公平な条件で下請けとして働いている人が実に多いです。
手抜き工事を生む不公平な下請け契約
下請けとして働く職人は、1日いくらではなく、1件いくらでの請負契約を結びます。多くが他にも仕事の当てがなく、計算も苦手なので、勤める場合よりも低い金額で請負っています。それらの金額を調べたところ、手抜きなく真面目に工事をすれば、社会保険料を加算すると当社社員でいるほうが手取りは多いです(当社計算)。なお、この金額は消費者の支払う金額には関係なく、例え高額な工事代金で消費者が発注していても元請が大半を取ってしまい、作業をする職人には還元されていません。
これは歩掛(人が施工できる平均の値)で計算していますので、ほとんど誤差なく算出できています。悪い会社は「ウチの職人は普通よりも一生懸命工事するので同じ時間で他よりも多く施工できます。」とウソぶくかもしれませんが、人が1日に出来る量には限界があり、”手抜きでもしないと”多く施工することは出来ません。外注扱いであるため車両や道具などは自己負担であるので勤めているよりも負担が多いにも関わらず、勤めているレベルの金額しか得られないのであれば、どうにかして勤めていた時よりも多く稼ごうとします。はじめの一回や二回は頑張れたとしても無理には限界があるので、元請け会社に分からないように手を抜く方法を職人間で共有するなどして、あっという間に手抜きを覚えます。要するに、手抜なしでは独立して稼げた感がない金額なので、必然的に手抜きが発生しやすい構造にあるのです。当たり前ですが、外注として扱われ、不公平な条件で働く職人たちには当然社会保険には加入してもらえません。当然ですが自らも加入することもありません。